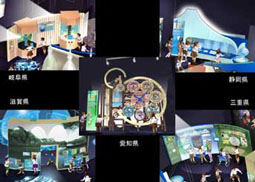中部千年共生村
コンセプト
1000年の冒険 中部の発見と創造
使い続けるといつかはなくなる地下資源。でも、この地球には千年先まで再生可能な資源があります。それは、皆さんのまわりにある植物や動物、昆虫などの生物資源です。中部千年共生村では、石油などの地下資源に頼れない千年先の子ども達にこの豊かな社会を引き継ぐため、「1000年先まで持続可能な社会」の実現を目指し、生物資源を活用した持続可能なモノづくりにチャレンジするとともに、優れた自然の営みを見つめ直します。
パビリオン概要
| 出展場所 | 長久手会場 日本ゾーン |
|---|---|
| 開館時間 | 3/25~4/25の期間:9時30分から20時30分まで 4/26~9/25の期間:9時00分から21時00分まで |
| 平均観覧所要時間 | 約20分間程度 |
| 収容人数 | 120人 |
| 予約の有無 | 無 |
| バリアフリー情報 | 多目的トイレがあります。 一部映像には字幕表示があります。 |
展示概要
生物の営みを支える「水」をモチーフに、「1000年先まで持続可能な社会」の実現を目指した提案を行います。館内では、優れた自然の営みや生物資源を活用したモノづくりの中から、中部9県が提案する、個性豊かな体感型展示物である「千年持続産品」のほか、巨大な水のドームがつくる不思議な空間「ミズノバ」や、通りかかる人に「まなざし」を向ける一つ目のロボット「サイクロプス」、体験型のワークショップなど、盛りだくさんの内容となっています。
ミズノバ ~アクア・マジック千年の旅~
水が弧を描いて落下する直径6mのドーム「ミズノバ」。一歩、中に足を踏み入れると、そこには異次元空間が広がります。水のスクリーンに映し出される映像ショーと清涼感が、全身を不思議な感覚で包み込みます。
千年アカデミアリーナ~中部9県の展示~
中部9県にある再生可能な「4つの力」 (植物力・昆虫力・動物力・微生物力)+「人間力」の活用と、それらを育んだ自然環境の中に、「千年持続品」を発見し、知り、学んでいただきます。展示は、映像やカラクリ人形、ロボットなどといった多様なコミュニケーション手法を用い、五感で体感できるものとなっています。
サイクロプス ~一つ目の観察者~
通りがかる人々に「まなざし」を向ける一つ目のロボット「サイクロプス」。名前の由来は、ギリシャ神話に登場する「一つ目の巨人」です。人間と同じような構造の背骨と50本の筋肉による「柔らかい動き」が特徴です。あなたを見つめたら、大きく体を動かしてみてください。
ワークショップ
中部9県の優れた知恵と技の伝統、先端技術、食文化をテーマに、「見て」、「触って」、「作って」、「味わって」、楽しく体験していただくコーナーです。中部9県が週替わりでテーマを設け、ワークショップを実施します。

ワークショップエリア・パース
パビリオンについて
千年持続社会への扉
パビリオンの外装材に中部9県の「和紙」とインドネシアの「黄金の繭」を組み合わせ、「中部千年共生村」を象徴する「生物資源」がイメージできるように工夫しています。また、夜間には内部照明によりパビリオン全体がやわらかな光で包み込まれ、「巨大な行灯」となります。

中部9県の和紙のパネル

黄金の繭
展示レイアウトについて
年齢・性別・障害の有無にかかわらず、分かりやすい内容と表現、見やすい展示を考えております。また、海外からの来場者にも対応できるよう英語併記の展示となっています。さらに、館内は段差を無くしたフルフラットの床面となっており、車椅子の方も余裕をもって観覧できる動線・スペースを確保し、バリアフリーな展示会場を目指しています。動線についても、スムーズな観覧誘導と緊急避難時を考慮した、分かりやすいものとしております。
環境への取り組み
中部千年共生村のコンセプトである「生物資源の象徴」の一例として、外壁に中部9県の「和紙」とインドネシアの「黄金の繭」を活用しました。「和紙」は中部9県の伝統的な和紙を用い、地域により異なる風合いを持つ和紙を組み合わせることで、外壁に変化を持たせています。また、「黄金の繭」は、インドネシアやマレーシア周辺に生息し、害虫とされているカイコ蛾の一種「クリキュラ」という野蚕の繭です。インドネシア共和国ジョグジャカルタ王室では、同国の低所得農業従事者の所得向上と伝統工業の育成のため、クリキュラを中心とした野蚕開発事業を進めており、「黄金の繭」の利用は、これらの取組みのPRの一役を担うことになり、地球環境保全への貢献につながるものと考えています。今回、このインドネシア産「黄金の繭」を、初めて外装材として使用します。
中部9県の「和紙」と「黄金の繭」の外壁

中部9県の「和紙」と「黄金の繭」