エコロジーレポート
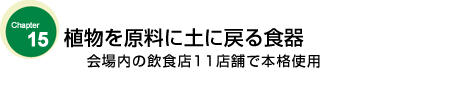
愛・地球博の飲食店で食事をした時には、使われているプラスチック食器にも注目してください。現在、ほとんどのプラスチックが、石油から作られていますが、万博会場内の大型レストランや、フードコート計11店舗で使用される食器は、植物を原料にしている「植物プラスチック」です。しかも、この植物プラスチックは、微生物の働きで分解されるという、大きな特徴を持っています。使い捨て型のプラスチック食器は、飲食施設から出る生ごみと一緒に処理され、堆肥(たいひ)に生まれ変わり、野菜や果物などを育てます。単に、環境にやさしいプラスチックを使うだけでなく、植物の再生までつなげた自然の循環再現を試みています。食器への植物プラスチックの大量導入、そのリサイクル、生ごみを含めた堆肥化では、世界的にも例がない事業規模となった、愛・地球博の「プラスチック食器事情」を探ってみました。
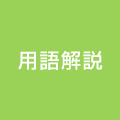
プラスチック
熱や圧力を加えて望みの形を作ることのできる軽くて丈夫な、無限に近い用途をもつ化合物がプラスチックです。別名「合成樹脂」といわれるように人間が作り出したものですが、現在、ほとんどが石油を原料とし、1960年代以降、工業製品や日用品の素材として不可欠なものになっています。しかし、限りある資源の石油を原料としているほか、腐らない廃プラスチックの処理が環境に大きな負荷を与えるようになっています。
最近、石油に依存せず環境に負担の少ないプラスチックの研究開発が進み、使用されだしています。特に植物を原料とするプラスチックが注目を集めていますが、廃棄後は植物と同じように、二酸化炭素と水に分解されるため、環境の視点からも普及が期待されています。このように最終的に二酸化炭素と水になるプラスチックは「生分解性プラスチック」と呼ばれます。
原料はトウモロコシからつくられる「ポリ乳酸」
愛・地球博で使われている植物プラスチックの食器の原料は、トウモロコシです。トウモロコシから採れるでんぷんを酵素などで分解し、糖化、乳酸発酵させ抽出した「ポリ乳酸」でつくられた「植物プラスチック」。不要となり地中に埋められても、自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解され、自然にかえることが特徴です。
二酸化炭素排出は、地球温暖化などで環境に害を及ぼすと思われますが、トウモロコシが光合成で吸収した二酸化炭素が、一時的に大気中に戻るだけです。新たに二酸化炭素が作り出されたわけでなく、自然界の循環サイクルそのものです。植物プラスチック活用による環境への貢献をまとめると、次のようになります。
- 大気中の二酸化炭素の増加を抑制
- 石油などの埋蔵量に限りのある化石資源を節約
→ 生物は毎年繰り返し育てられるので持続的に利用できます - 微生物が水と二酸化炭素に分解
→ 廃プラスチック処理に必要な埋め立て地不足解消に貢献します - 燃やしてもダイオキシンなどの有害物質の発生なし
→ さらに焼却しても燃焼温度が低く、焼却炉を傷めません - 製造時の必要エネルギーは従来品の約半分
植物プラスチックごみ袋使用で、堆肥化が容易に
植物プラスチック食器は、長久手会場内11の飲食施設で使われています。皿や丼など何度も使えるように強度を高めた「リターナブル型」と、ドリンクカップやパックといった「使い捨て型」の2種類があります。使用個数はリターナブル食器が25種類、約12万個、使い捨て食器は24種類、約2000万個にも及び、次のようにリサイクルされます。
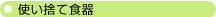

【写真3】使い捨て食器 |
植物プラスチックのごみ袋を使用し、 食べ残しなどの生ごみと一緒に回収し、会場外へ (ごみ袋も分解されるため、袋ごと堆肥化することが可能に)

一緒に約半年かけて、微生物の力で生ごみを分解させ堆肥に
(バイオリサイクル)

この堆肥を使って、愛知県・東海市の農家で、 ナス、タマネギ、イチジク、ブドウ、花を栽培(堆肥化は2004年度から実証実験開始)

【写真4】堆肥を使って野菜や果物を栽培する畑

会場内の飲食施設で食材として使用
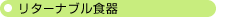

【写真1】リターナブル食器
破損した食器を回収し、会場外へ

砕いて溶かし再び製品化
(マテリアルリサイクル)
→トレイや植物ポットなどの生活資材や農業用資材として再利用

【写真2】右のトレイは左のジョッキを再利用したもの

(最終的には水と二酸化炭素に分解)
試作品テストを経て最終導入食器を決定
新しい試みとあって、飲食施設側でも、食器の種類・形の検討から始まり、試作品のテストを何度も繰り返しています。例えば、熱い料理にどのくらい耐えられるか、放置後どのくらいで変色してしまうかなどの確認を行い、最終的に導入される食器が決まりました。
会場内の西エントランスにある200席の大型飲食施設「うまいもんや にっぽん」では「食器によりメニューが制限されることも生じましたが、大量に使わないもの以外はすべて植物プラスチック食器を使用しています。賛同して取り組んでいることからも、お客様から食器を尋ねられたときも、できる限り説明しています」と導入の意義を強調しています。
飲食施設では「おおむね通常のプラスチックと同じように使えます」というものの、植物プラスチック食器の本格普及について、次のような課題を指摘しています。
- 欠けやすい…陶器よりは丈夫ですが、丼のふちや下部分が欠けやすく、表面もはがれやすい
- 高熱に弱い…油ものは、油切りを通常よりも念入りに工夫しています
- 変色しやすい…カレーの香辛料や、ナスなど植物の色素で変色しやすい。漂白剤が使えないので、繰り返し使うことに限度があります

【写真5】欠けた丼と変色した皿
市場規模は10年間で50倍と予測
従来のプラスチック製食器は、強度や耐久性、量産性、安価の利点から広く普及しました。一方、植物プラスチック食器は、耐熱性などで改善の余地が、まだまだあります。
しかし、「植物プラスチック」全体で見れば、耐熱性については、ほかの樹脂と混ぜるなどして技術革新が進み、電子レンジで加熱できるものも出てきています。コスト高解消に向けては、「ポリ乳酸」の原料がトウモロコシだけでなく、サトウダイコン、サトウキビ、サツマイモなども利用できるようになったほか、ポリ乳酸の大量生産も確立してきました。
さらに成型時の精度があがれば、需要分野が広がりますが、日本の関連企業約200社で作る団体「生分解性プラスチック研究会」は、(1)量産体制を整えてのコスト減 (2)堆肥化のインフラ整備 (3)消費者に実利を示すこと--の重要性を指摘しています。そして、市場規模は、2000年4千トンから2003年には1.5万トンまで拡大し、将来的に2010年には20万トンとなると予測しています。
こうした確実な市場の拡大が見込まれているように、身近な分野での植物プラスチックの実用化が進んでいます。すでに ▽タオルや肌着、歯ブラシ ▽パソコン本体の筐体 ▽車の内装材 ▽食品包装用のフィルム・容器 ▽紙オムツ--などが身近な製品となっています。
会場内案内図、標識にも使用
従来のプラスチックの領域をほぼ代替えできることから、会場内では植物プラスチックが「ごみ袋」をはじめ、「会場内の案内図」「会場内の標識」「パビリオンの外装・内装材」などに使用されています。数的にもごみ袋が約80万枚、案内図は約500枚、標識は550カ所です。
特に「ごみ袋」は、生ごみを堆肥化する際に、袋から取り出す必要なく再資源化できるほか、可燃物と一緒に燃やしても燃焼温度が低く、焼却炉を傷めないとして、今後の普及が期待されます。

【写真6】ごみ袋

【写真7】会場内の案内図

【写真8】会場内の標識

【写真9】日本館の外装
国の戦略に大規模な実行の機会
愛・地球博における「植物プラスチック」の導入は、2002年12月に閣議決定された、動植物からエネルギー源や製品を得ようという『バイオマス・ニッポン総合戦略』に盛り込まれています。資源を有効活用する循環型社会の実現を目指す、国をあげての実証研究の一環として、環境万博を掲げる愛・地球博が具体的な大規模実行の機会の場です。この成果は確実に万博後にも引き継がれていきます。

【写真10】植物プラスチック食器を分かりやすく明記したごみ箱

【写真11】植物プラスチック導入をPRする看板と堆肥で育った花
「植物プラスチック」の食器を導入している店舗一覧
- ホテルオークラ中国料理 「桃花林」
- 寿司処角
- フェスティバル フードコート
- ピーロート・ワールド フード&ワインコート
- うまいもんやにっぽん
- クイーン・アリス アクア カフェ
- レストラン ビア・ハーレ
- 神楽坂 トルコレストラン ソフラ
- コリアレストラン 韓一亭
- ワールドレストラン
- アサヒパノラマレストラン
